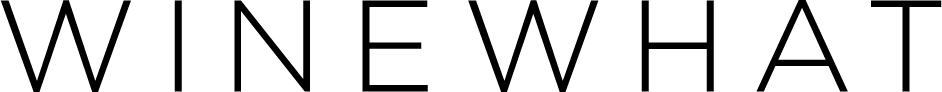Feel the Earth
フィンランドのヘルシンキ空港を経由して、アイスランドのレイキャヴィーク空港に降り立ったのは夕方だった。
朝、成田を発ってから、すでに半日以上が経過しているにもかかわらず、9月14日はまだまだ終わらない。周囲は、空港と駐車場と道路をのぞけば、人工物はない。太陽は低い。空を覆う鈍色の雲の切れ目から、地を這うように、夕暮れ時とはおもえない冴えた陽光がさしている。横からくるその光によって周囲は清かに輝くけれど、熱は感じられず、気温は5℃くらいしかない。地平線までつづく、土というより岩のようなごつごつした陸地を覆うのは、薄緑色の苔のような下草で、合間合間に白けた色をのぞかせる。遥かに望む山々は、尖った部分を古の氷河によってごっそりもっていかれてしまったため、角のまるまった台形をしていて、その裾野からは、時に、白くうすいモヤが、雲に導かれるように立ち上る。マグマや温水の噴出口でもあるという出自を物語っているのだ。
空港からクルマで約1時間。そんな風景のなかを走りつづけると、一種のやすらぎを感じた。ここは生命が希薄だ。アイスランドの荒野に立てば、そこあるのは命の喧騒ではなく、いまだ冷却には遠い、若い地球の鼓動だと感じる。だからここに生きるものは、ともすれば現在の地球生命が忘れかけている、生きることの原初的なありかたを体現しているのかもしれない。守り慈しんでくれる母なる地球がここにはないから、自分が生きているのだ、という実感がえられる。それがやすらぎになる。弱い生命の代名詞たる羊すらも、ここではそんな生き方が常態なのではないだろか。
アイスランドは人口33万人。そのうちの2/3が、103,000 km²の国土にたいして、1,052 km²しかないレイキャヴィーク地方にすみ、さらにそのうちの半数以上が、274.5 km²のこぢんまりとした港町、レイキャヴィーク市内に住むのも、一処によりそうことで、生命の希薄に抗おうとしているかのようだ。厳しい自然は、電力の7割を水力で、3割を地熱でまかなうことを可能にする。2010年、2011年と、立て続けにおきた大規模な火山活動によって、ヨーロッパの航空機の運航を大いに混乱させたことがきっかけとなり、存在が知られてからは、訪問客がふえ、いまやその数は200万人にも達し、宿は不足して、開発が進んでいる。
レイキャヴィーク市は密集した都市だ
怪我の功名か大地の恵みか、かくして注目を集め、グローバリズムに直面するアイスランドは、インバウンドと同時に、いくつかの産業がアウトバウンドを狙っている。前置きが長くなったけれど、今回、ぼくがこの地を訪れた理由は、アイスランドが現在、輸出に力をいれている、羊を知るためだ。