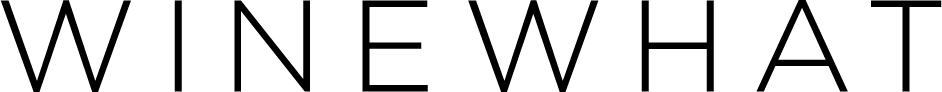赤ワインはピノ・ノワールを2種
「次は色をあわせる、というペアリングです。アルザスの甘いワインと洋梨やりんごのコンポート。パイナップル、マンゴー、あるいははちみつと、ソーテルヌ。合いますよね。ワインの色と食べ物の色を合わせるというのもペアリングの基本なのです。かぼちゃなども、色がしっかりしていますから、白ではなく赤のほうが合う場合もあります」
ペトリュス氏は、ビーツと生クリームのムースの上に、出汁を加えた料理に、先ほどとおなじロワールながらサンセールのピノ・ノワールを合わせた。サンセールといえば、それこそ、ソーヴィニヨン・ブランの聖地のようなところではないか! これはそこのピノ・ノワール。造ってたんですねぇ。
「サンセールはロワールでも、ロワール右岸のピュイィ・フュメとは土壌が違い、石灰の影響でピノ・ノワールから繊細な赤ワインが造れます。赤ワインを造っていることすら、知らない方もいらっしゃる、白ワインで有名な産地ですが、この「ドメーヌ・ヴァシュロン」の「サンセール・ルージュ」は、目をつぶって口に入れると、白ワインのようではないですか? タンニンは優しく、甘みは少なく、デリケートでエレガント。クリームのなめらかさ、出汁のやさしい塩味と合い、そして、それらの香りを広げてくれます」
これもまたおっしゃるとおり。単に色だけでなく、食感も味もドンピシャ。ビーツの甘み、全体の食感のクリーミーさ、そして、出汁のうまみ。ワインにもそれらの要素があり、ワインと食に一体感がある。調味料と料理の関係のよう、とも言えるかもしれない。
「ムースのリッチさを感じているところで、ワインを口に入れてください。酸が調和します。ペアリングでは、飲むタイミングも大切なのです」
さらに、ペトリュス氏は赤ワインのサーブの仕方についても言及した。
「赤ワインは14度くらいが適温です。室温、といいますが、フランスの室温よりやや低め。徐々に少し高まるのが理想です。とはいえ、最高で16度くらいまでとしたいところです。ピノ・ノワール、ガメイ、モンドゥーズ、一部のシラーなど繊細なワインは、できれば14度を最高温度としたいです」
「また、フランスではデカンタというのは、定番の文化。特にヴィンテージもののワインについては、なされるもの、という認識が一般的ですが、ヴィンテージワインやこういった繊細なワインについては注意が必要だとおもいます。ワインが空気にふれ酸化することで、香りが失われ、タンニンが強く出すぎてしまう危険性があるからです。今回は、若々しさが失われないよう、デカンタせず、大きいグラスでサーブすることにしました。それでもファーストノートとセカンドノートは変わってきます」
そこで筆者、ちょっと疑問が生まれた。ペトリュス氏がデカンタは好ましくないとおもうワインに、お客さんがデカンタを望んだ場合、あるいはそもそもこのワインはこの料理には合わない、とおもうワインを注文された場合はどうするのだろうか。
「もちろん、お客様のご要望が優先です。そこは我々がでしゃばるところではありません。ただ、むしろタイユヴァンでは、リストに2000種類以上ワインがありますから、お客様から、こういうワインが飲みたいけれど、どんな食事がいいですか? と質問されたり、知らない産地のものを試したい、とか、好みとは全然別のタイプのワインを飲んでみたい、と言われることのほうがおおいかもしれません。それは、刺激的で、私にとっては天国みたいな職場です。そして、お客様がどう、ワインを楽しみたいかとともに、私は、ワインを造った人が、どうワインを飲んでほしいか、も考えます」

今回のワイン、左からコレクション・タイユヴァン シャンパーニュ ドゥーツ ブリュット、パスカル・ジョリヴェ プイィ・フュメ、ドメーヌ・ヴァシュロン サンセール・ルージュ(2012年ヴィンテージ)、そして、ドメーヌ・ラペ アロース・コルトン(2011年ヴィンテージ)
さて、最後に締めの一本。ここはちょっとヘビー目で。ブルゴーニュのドメーヌ「ラペ」から、「アロース・コルトン」 2011年。料理はブルゴーニュの定番ともいえる、牛肉のワイン煮込みブフ・ブルギニオンだ。訳せば「ブルゴーニュの牛」となる。
「アロース・コルトンは、ブルゴーニュの赤ワインとはいえ、コート・ド・ニュイではなく、その少し南のコート・ド・ボーヌです。コート・ド・ニュイのピノ・ノワールはクリアで、力強く、芳しく、デリケートでバランスがいい。赤系果実のブーケのようです。先程のサンセールもこれに近いキャラクター。一方、コート・ド・ボーヌは、粘土質の土壌がやや増えて、タンニンの質も変わり、チェリー、ラズベリーなど、黒い果実のイメージ。スパイスも感じられます」
まったくもってそのとおり。ピノ・ノワールの繊細さがありつつ、タンニンがしっかりしていて、どこかスモーキーな印象もある。たしかに、ブフ・ブルギニョンと合うけれど、そのこころは?
「ブフ・ブルギニョンはフランスのクラシカルな料理で、シチューの一種ですが、料理につかう赤ワインをテーブルで料理と一緒に飲むのが、相性が良いとされます。ここでもそれです。そして、キーワードはリージョナリティ。地域性です。よいワインの産地にはよい料理あり。プロヴァンス、ロワール、アルザス。いずれもワイン名産地で、ガストロノミーの地です。食事のためにワインが生まれ、ワインが食事を、食事がワインを、と互いに影響をあたえていった地です。ボルドーに赤が多いのはボルドーの料理が赤に合うから。魚でも赤ワインのソースをつかったりします。アルザスにはピノ・ノワールが少なく、かわりに仔牛とかチキンにあう白ワインがあります。ジュラのワインもコンテチーズに合う。ブフ・ブルギニョンはブルゴーニュの赤ワインに合うのです」
削り込むペアリング
かくして、シミラリティ(類似性)、オポジット(対照)、色、リージョナリティ(地域性)と4つのキーワードで描かれた、ペトリュス氏による「食とワインの調和」入門。筆者が冒頭、「想像していたのとはちがっていた」と言っていたのは、ペトリュス氏のペアリングが、研ぎ澄ますスタイルだと感じたからだ。
料理もワインも、味、香り、見た目のさまざまな要素が絡み合ってできている。食とワインの調和、と言ったときには、特にそれが、フランスの伝統的なレストランのペアリングとあれば、さまざまな要素が、わっと口のなかで花開き、膨らむような、1+1が10になるようなペアリングを想像していた。
ところがペトリュス氏のペアリングは、そうではない、と筆者は感じた。
どちらかと言うと、引き算。料理とワインが協調して、一つのピントの合った映像を描き出すかのような印象を受けた。10+10で1をつくるかのよう。カメラでいえば、単焦点のポートレートのように、背景にある雑多な情報は、そもそも映像のなかに入れないか、入ってもぼかしてしまい、表現したい人物を、引き立たせて描くかのようだ。
はたして、パリのタイユヴァンでペトリュス氏のペアリングを体験することが出来たときにもおなじ印象を抱くのか? 一度は、それを体験したいものである。
いっぽう、今回、筆者が体験したような「食とワインの調和」については、ペトリュス氏はおらずとも、ペトリュス氏が監修している「レ・カーヴ・ド・タイユヴァン 東京」にて体験できるので、筆者の言っていることが本当かどうか、読者の皆様の舌と鼻と目で、確かめてみていただきたい次第だ。