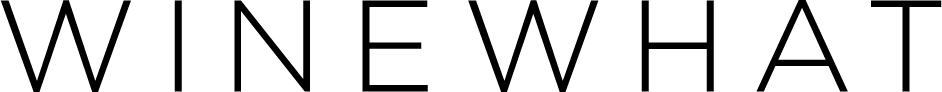「勘性」を磨いてこそ
のどにおいしいものが通った瞬間、それはとても満ち足りた感覚です。けれど、その瞬間から喜びは次第に失せていく。食べ物だけではなく洋服も同じ。最初に袖を通した時と同じ喜びは10回目には決して味わえない。でももしかすると10回目には最初の時とは違う、愛おしさを感じているかもしれない。
一流とか老舗とかいう表現での評価は、一体誰が決めているのか。成るほど確かに、昨日オープンしたばかりの店と10年、50年と続いている店では、経験の蓄積が違います。新規店にベテランが入っても、チームワークが生まれなければ一人では何ともならない。けれど何十年も続いた店でも、謙虚に努力し続ける店と、歴史や名声の上にあぐらをかいている店では差が出てきます。昨日オープンした店も切磋琢磨し続けたなら1年後には上をいくかもしれない。自分ではない人間が口にした一流とか老舗という言葉を、安易に鵜呑みにして使ってしまうのでは、永遠に自分のメジャー=尺度というものを作れないままで終わってしまいます。
ピタゴラスが新しい定理を発見するのとは違って、おいしい料理店がどこにあるか、机に向かっていても突如ひらめくわけがありません。友人からの情報、ガイドブック、あるいは顔馴染みの料理人から聞いた独立情報。その店の場所や外観の印象もあるでしょう。
でもどんなにか情報を集めたところで、本当に「真っ当」なものに出逢えるかどうか、それは自分次第なのです。最終的には自分の五感が「これはまがい物か否か?」を見抜けるかどうかなのです。そうした「感性」ならぬ「勘性」を、失敗しながら場数を踏んで磨いてこそ、唯我独尊とは違う「自分のなかの真っ当とは何か」の尺度を創り上げていけるのです。
失敗は立派な学習です
今から38年前の1976年、大学2年生の私は知り合ったばかりのガールフレンドと、六本木にあった「イル・ド・フランス」という店にでかけました。当時のフレンチはホテルが主流で、街場には数えるほどしかなかった時代。ガイドブックには「この店はボジョレーワインがお手頃でおすすめ」と書いてありました。で、疑いも無く21歳の僕は注文するわけです。それも5月か6月にね。
サーヴィスの方は「同じ価格帯のこちらはいかがですか?」と別のワインを勧めて下さった。でも、僕は「ボジョレー」と言い張ったのです。だって、ガイドブックにそう書いてあったから(笑)。
ボジョレー・ヌーヴォーのブームなんて影も形も無かった時代とはいえ、今やコンビニにも売っているワインに田中康夫が固執していたなんてね。もちろん、その「ワインはヌーヴォーでなく、ヴィラージュだったのでしょうけど。でもね、思わず嗤っちゃったあなたにも、思い返せば、ちょっぴり恥ずかしい思い込みの失敗がきっとあるはず。でも、それは決してダメなことじゃない。立派な学習なのです。
早い話が、恋愛を一度もしたことがなくて恋愛小説を書けるわけがない。科学の知識なしに、SF小説は書けない。だけど数十人と恋愛を重ねても、自分の中で恋愛を相対化できない、恋愛観を語れない人もいるわけですよ。
このワインがおすすめだとソムリエが語るのは「知識」だけれど、その知識を鵜呑みにし続けるのではなく、失敗しながら、トライ&エラーの経験の中から「自分の判断の尺度」を育てていく。それが、必要で大切なのです。
ですから、情報を得たときに虚心坦懐にすべてをフラットな地平に置いて、そこにある情報を、自分の今までの知識と経験の引き出しの中でどこに位置づけるか。こうした永遠の練習の繰り返し。それを厭わずに日々、行ない続けなくては、いつまで経っても「自分の尺度」は構築出来ません。恋愛も食事もワインも、単に数をこなしただけで、自分自身の中で相対化できなければ、スタンプラリーのスタンプの数だけが自慢なのと同じになってしまいます。
知識と経験に優劣なし
知事になる前から僕は「三位一体の利潤」という言葉を繰り返し用いていました。料理ならば「作り手、供し手、食べ手」を指します。商品ならば「作り手、売り手、買い手」。これら三者が一体となって、数字に換算できない部分まで含めた、満足や充実、ありがたさを追求する。それが三位一体の利潤です。なのに「格差社会」の実現に向けて日夜努力されている竹中平蔵さんが、この僕の造語を〝誤用〟して「三位一体の改革」と言い始めたのでイメージがずれてしまいました(涙)。話を戻すと、今も昔もなぜか作り手、あるいは売り手が上から目線で、あるいは逆に食べ手や買い手が高みに立って、妙にギスギスした二等辺三角形になることが多い。だがこれではハッピーな三角形としての「三位一体の利潤」ではないのです。
慎み深い=ディーセント(decent)な気持ちが三位一体には不可欠です。でも、その一方で恋愛も食事も、ケミストリー=相性が大切。誰もが称賛する異性、礼賛する料理も、自分としては今一つしっくりこないことがあります。なのに、八頭身やアルカイックスマイルだから評価せよ、認められないお前がヘンだ、と料理やワインに関しても決め付けられたら、ゲンナリしちゃうでしょ。もちろん、「今までの人はこう言ってきた。でも自分の尺度ではこうだ」と説明出来るだけの言葉を持ち合わせなければ、それまでの世間での「評価」に屈することになってしまうのですが。
一例を挙げれば、ポール・ボキューズと日本料理との出合いがヌーヴェル・キュイジーヌ誕生の発端だと言われてします。でも彼は実際に八寸を見た瞬間、食べた瞬間、ひらめていたわけです。今までの知識になかったものを経験した瞬間、自分の勘どころ、つまり「勘性」の回路が結び付いて、新潮流が生まれたのだと思います。
他方で、知識と経験では前者の方が格上だと思われがち。でも、本来その二つに優劣はないんです。そうして、未知のものと出合った瞬間、自分の引き出しの中から、どの知識や経験を持ち出してきて、温故知新で新しい「自分の尺度」を研ぎ澄ませるか。勘どころの勘性です。でないと、あっという間に、先ほども申し上げた「さすがは一流の老舗ならではの味」という、誰だか知らない人の評価に追従するようになってしまう。これでは自分自身の成長も成熟もないのです。
ワインは女性に喩えられる
目利きであることに加えて、鼻利きであることも大切です。客室乗務員がまだスッチーと呼ばれていた時代、彼女たちの間でソムリエの資格を取るのが流行りました。でも、どんなにか知識が増えようとも、自分の言葉でワインを表現出来ないのでは、単なる偏差値教育と同じ資格の取得で終わってしまいます。
田崎真也氏に個人授業を受ける形式で80年代の終わりから連載していた対談を『ソムリエに訊け』という本に纏めているのですが、その中で当時の僕は「ワインは女性の体躯に喩えられる」と語っています。
赤ワインは気位の高い低血圧な女性です。カーヴから取り出すや抜栓して飲もうとしたなら、「何よ愛撫もなしで、目覚めてもいない私を、飲もうとするなんて許せないわ。脚を開く気にもなれない」とタニックな味わいで抵抗するでしょ。
ボルドーでもマルゴーは良くも悪くも肉感的なレースクイーン的な体躯。ポイヤックは抜栓直後は土の薫りがする農夫の娘。でも育て上げると美しい娘に変身を遂げる。海に近いサンテステフはリゾートに滞在している都会の娘だけど、少し肌はざらついてるとか。
こういう説明に対して、「下品!」と嫌がる人もいれば、面白がる人もいる。一見、乱暴に聞こえるかも知れませんが、要は教科書とは違う、自分の表現を創り出しましょうということ。
信州で知事になって取り組んだのが「長野県原産地呼称管理制度」です。それは但馬牛、淡路牛の呼称ならいざ知らず、肉牛肥育業者は六甲山の裏側にわずか数軒なのに全国の百貨店で「神戸牛」を名乗って売っているのは原産地「偽呼称」ではないかと疑問を抱いていたのが切っ掛けです。
葡萄品種に加えて最低糖度、補糖限度等の数値基準を設け、栽培・採取・破砕・圧縮・発酵・熟成・濾過・瓶詰・出荷の工程全てが県内完結の客観条件を構築しました。その上で、官能審査で毎年、認定の可否が決定する切磋琢磨の制度です。ワインだけでなく、日本酒、米、焼酎、シードルにも導入しました。
一旦、格付けされると半永久的に格付けが固定化されてしまう従来のアペラシオンとの違いです。そうして、その官能審査を行う審査員も絶対なわけではありません。ある意味では官能審査は審査委員会の主観ともいえるのです。つまり、数値基準や客観条件、そして官能審査を経た評価に対して、今度は一人ひとりの飲み手が「自分の尺度」で評価を下すのです。
人間が付ける98点と97点のわずか1点の差にどんな客観性があるのか。ロバート・パーカーに代表される数値かを否定するのではなく、それを鵜呑みにしたまま、「自分の尺度」を構築し得ない我々の側が試されているのです。
それは「行間を読み取る」訓練とも言えます。でないと、「さすがは一流の老舗ならではの味」をあがめ奉るのと同じになってしまいます。あくまでも自然体で、今まで耳にしたサジェスチョンや評価も耳に入れながら、最後は自分が決めるべきなんです。
「自分の尺度」を「自分の言葉」で
かつては「スペック」を重視するのは男性でしたが、最近は女性の中にもそういう人が増えてしまいましたね。いわば、数値で表現可能な形式知。本来、料理やワインは暗黙知で語るものだったのにね。暗黙知とは、言葉にうまく言い表せないけれど、でも、明らかに、確かに、そうなのだと実感出来ること。言い換えれば、「地頭」。つまり、自分で考え、自分で語り、自分で動く。
でもね、子供が補助輪なしで最初から自転車に乗れるわけがないように、私たちも最初から料理やワインを失敗せずに選べるわけもない。上から目線ではない「先生」が、「自分の尺度」を作る過程では必要です。でも、その「先生」を選ぶのも自分の勘性です。相性=ケミストリーの合う、そうして優しく、けれども甘やかさずに自分を育んでくれる「この人の言うことは感覚、相性として合う」という人物と巡り会うことがワインに於いても肝要ですよね。
なあんて大層な話をしてきましたが、実はいまだに僕もトライアル&エラーならぬエラー&エラーかも知れません。でも、「自分の尺度」を「自分の言葉」で語れるようになろうとする意欲。この気持ちを常に持ち続けることは大切ですね。